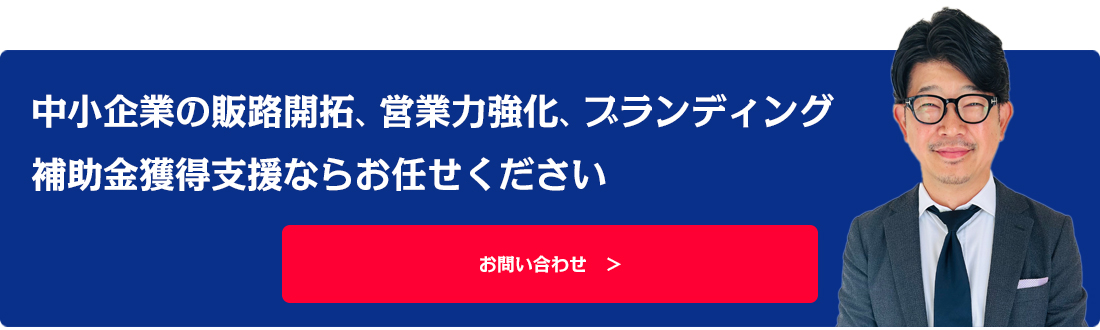皆さんこんにちは!中小企業営業支援の津山淳二です。中小企業向けに営業強化、ブランディング、補助金支援を行なっております。
先日オンライン商談会に出展する事業者様向けにセミナーを開催しましたので、その内容を全7回のシリーズで説明をしていきたいと思います。
今後、展示会や商談会は、リアルとオンラインのハイブリッド型が主流になると思われます。
これはコロナウィルスが収束したとしても、オンラインを使った商談は利便性の観点からも無くならないからです。

なのでここでオンライン商談のコツをまとめておきますね。
全7回の内容は以下の通りです。
1.オンライン上で伝わるテクニック
2.BtoB営業の特性を理解する
3.シナリオを作ろう
4.商談相手の知りたいことは何だろう?
5.仮説を立てよう!
6.ヒアリングのコツとは?
7.アフターフォローの重要性
では今回は第2回目として「BtoB営業の特性を理解する」をお伝えします。
オンライン商談会で、出展する事業者が商談する相手は、企業に所属するバイヤーや購買担当になります。いわゆるBtoB営業(法人営業)ですね。BtoC営業(一般消費者向け営業)ではありません。
よって「BtoB営業の特性」を押さえておく必要があります。
私が考えるポイントは以下の4つです。
①バイヤーが最終意思決定者とは限らない
商談相手は法人です。個人ではなく組織です。つまり商談相手の役職により権限が異なります。もちろんバイヤーや購買担当がそのまま購買決定者の場合がありますが、全てそうではありません。バイヤーの上司、もしくはその会社の役員等が最終的な意思決定を行なう場合があります。よって商談する企業の意思決定プロセス(誰が最終的な意思決定者なのか?どのタイミング、会議で決定するのか?等)を商談時に確認することが重要です。
②感情的な意思決定はない
BtoC営業(一般消費者向け営業)では、一時の「感情」や「ひらめき」「直感」で購買決定されることがありますが、BtoB営業(法人営業)ではほぼゼロです。相手は組織なので、当然なぜその会社に決めるのか?合理的な理由が必要です。その企業が持つ商品やサービス、対応力、価格、信用度等購買を決定する項目は各々ですが、組織として購買決定するにはその理由が明確なはずです。よって相手の企業が何を重視しているか?購買決定要因を常に探るようにしましょう。こういった情報は、相手が上場企業の場合、IR資料や決算報告書などに経営戦略や事業戦略をヒントにすることも有効です。

③導入検討には時間がかかる
対象企業の意思決定プロセスによりますが、初回商談から取引開始まで比較的時間がかかるケースが多いです。これはバイヤーや購買担当の検討フェーズに関係します。検討フェーズには問題解決ニーズ発生、情報収集、業者選定、購買決定があり、またそのスピードもその企業の経営戦略に紐づきます。企業のTOPが変わって急に戦略が変わり、導入が延期になったという話も珍しくありません。
④長期的な取引が前提である
こうやってみるとBtoB営業(法人営業)は非常に手間と時間がかかることがわかります。相手は組織なのでそれだけの検討プロセスを踏んで取引を決めるわけですね。逆に言えば、一度取引が決まれば、よほどのことがなければ取引が消滅することはありません。組織であるがゆえに今度は取引を止めるにも組織を納得させる合理的理由が必要です。一般的に業者変更というのは、相手企業の手間が大きくなるため、担当者レベルでは嫌がるケースの方が多いのです。

以上から、BtoB営業(法人営業)というのは、常に相手の経営戦略を注視しながら長期的な視点を持って取り組む必要があります。この特性を踏まえ、オンライン商談に臨むといいでしょう。