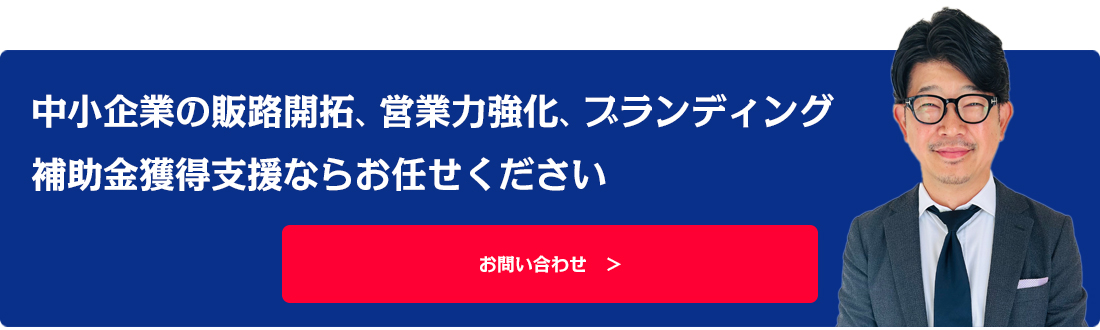皆さんこんにちは!中小企業営業支援の津山淳二です。中小企業向けに営業強化、ブランディング、補助金支援を行なっております。
ついに、「事業再構築指針」がでましたね!
ミラサポプラスのサイトに今日掲載されました。
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/11458/
手引きはこちらです。33ページもあります。。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf
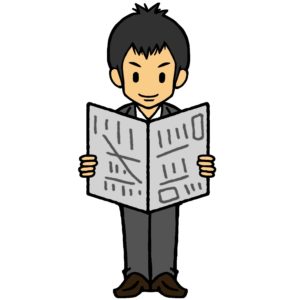
注目度の高い補助金の指針ということもあって、いつ公開になるのか待ちわびた関係者も多かったと思いますが、一言でいって、かなりややこしいです。。
多くのYouTubeやブログなどでは、予算が1兆円を超えるということもあり、かなり緩い条件になるという予想がありました。しかしながら蓋を開けると、細かい条件が設定されており、個人的な見解ですが、気軽に申請できる内容とは思えませんでした。
とにかくまずは。この「事業再構築指針」を解説していきましょう!

まずは「事業再構築」の定義です。
事業再構築とは、①「新分野展開」、②「事業転換」、③「業種転換」、④「業態転換」、⑤「事業再編」の5つに定義されてます。
①「新分野展開」・・・新たな製品を製造し、新たな市場に進出すること。
例)航空機用部品を製造していた事業者が、医療機器部品を製造する、ウィークリーマンション経営者がレンタルオフィス業をはじめる
②「事業転換」・・・主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること。要するに飲食業のままだけど、日本食屋から焼肉屋へ事業を転換することです。
例)日本料理屋が焼き肉屋に事業転換、プレス加工用金型製造業が産業用ロボット製造業に事業転換
③「業種転換」・・・主たる業種を変更すること。例えば、卸売業から製造業へ転換を図ることです。
例)レンタカー事業者が、貸切ペンション事業者へ業種転換、生産用機械製造業がデータセンター事業者へ転換
④「業態転換」・・・製品等の製造方法等を相当程度変更すること。要するに、新たな製造方法で新たな製品作るか、サービスであれば新たな提供方法を確立することです。
ヨガ教室がオンラインヨガ教室へ業態転換、健康器具製造業者がさらに付加価値の高い健康器具を製造
⑤「事業再編」・・・会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換のいずれかを行うこと
⑤は組織再編行為+①~④のどれかを足し合わせるってことなので、詳細な説明を省きますが、まず定義の理解だけでも大変ですね。。

私の個人的な印象ですが、②の「事業転換」や、③の「業種転換」っていうのはハードルが高い印象です。多くの企業は既存事業の延長で設備投資を考えている会社がほとんどでしょう。設備投資の動機も既存設備の入替需要が多いかと思います。
現時点での私見ですが、検討しやすいのは以下の2つと思います。
①「新分野展開」・・・新たな製品を製造し、新たな市場に進出すること。
④「業態転換」・・・製品等の製造方法等を相当程度変更すること。
上記の内容であれば、経営革新計画や、ものづくり補助金等の要件に近い形になるのではないかと
思いますがいかがでしょうか?
では、さらに細かい条件を見ていきましょう。
まず①の「新分野展開」です。
その場合、以下の7つの条件が揃わないと「事業再構築」に該当しないということになります。
1)過去に製造していない製品である
もうすでに製造している製品は対象外です。
2)主要な設備は変更する
既存設備で製造するのは対象外です。
3)競合の多くがやっていない
これは、既存製品との組み合わせで考えるようです。要するに、医療機器部品単体で考えるのではなく、航空機用部品+医療機器部品の組み合わせで考えるようですね。
4)定量的な性能や効能が異なる
計測できれば提示し、できなければできない理由を述べるそうです。うーん。わかりづらい。
5)既存製品等と新製品等の代替性が低いこと
用途が異なったり、関連性が低いことを説明する必要があります。
6)客層が異なる
これは任意条件ですが、客層が異なることを説明する必要があります。
7)新製品の売上が総売上の10%以上になる計画を策定している
あくまでも3-5年後の事業計画終了後のことです。問題は達成できなかった場合のペナルティの有無ですね。ちなみに今回の指針にはペナルティについての表記はありませんでした。
申請書には、7つの条件を何らかの形で合理的な説明が必要になるでしょう。よって申請書類は結構な分量が予想されます。
ちなみにハードルが高そうな②「事業転換」③「業種転換」ですが、上記7つの条件のうち1)~6)までは同じで、7)だけが異なります。
7)は総売上10%ではなく、該当する新たな「事業」や「業種」の売上が最も高くならなければなりません。ただしあくまでも計画上の話なので、達成できなかった場合のペナルティが気になるところですね。

最後に④「業態転換」の説明をします。
ここが結構ややこしいです。。
大きく言うと、対象が製品なのかサービスなのかで異なります。
製品の場合は、9つの条件をクリアする必要があります。
サービスの場合は、6つの条件をクリアする必要があります。
製品の場合
1)過去にやっていない製造方法である
過去に実施している製造方法であれば対象外です。
2)設備を変更すること
既存設備のままでは対象外です。
3)競合の多くがやっていない製造方法であること
ここもしっかり合理的な説明ができればいいでしょう。
4)定量的に性能又は効能が異なる製造方法であること
数値を提示可能であれば説明し、不可能であれば、提示できない理由を書くようです。
5)過去に製造していない製品であること
既に作っている製品は対象外です。
6)設備を変更すること
新たな設備を入れる必要があります。
7)競合の多くが製造していない製品であること
8)定量的に性能又は効能が異なる製品であること
9)新たな製造方法で生産する新製品で総売上の10%以上になる事業計画を策定すること
ここはあくまでも計画なので、他の定義と同様ペナルティ次第でしょう。
サービスの場合
1)過去にやっていないサービスの提供方法である
もうすでに実施済みであれば対象外です。
2)設備を変更すること
新たな設備投資が必要です。
3)競合の多くがやっていない提供方法であること
あくまでもそれを説明できればいいそうです。まあオンラインでの提供がパターンとしては多くなると思いますが、今更感は否めないですね。。
4)定量的に性能又は効能が異なる提供方法であること
これも提示可能であれば説明し、不可能であれば、不可能な理由を書くようです。
5)既存設備の撤去や既存店舗の縮小等を伴うものまたはデジタル技術を活用した非対面化、無人化・省人化、自動化、最適化になるもの
ここが他の条件にはないですね。要するにサービス提供方法を変更するのであれば、既存事業の縮小かITツールを使った取り組みが必要ということです。
6)新たな提供方法でのサービスで総売上の10%以上になる事業計画を策定すること
ここはあくまでも計画なので、他の定義と同様ペナルティ次第でしょう。
となります。

とまあ、ざっと説明しましたが、事業再構築指針の手引きは33ページもありますので、まずは皆さんじっくり読んで、自社の事業計画と指針が合うのかどうかを見極める必要があるでしょう。
もちろんこれは自社だけで判断するのではなく、認定支援機関にも相談して、最終的には認定支援機関の承認のもと申請することになると思います。
認定支援機関側も、これらの条件をクリアしていることを承認する作業も容易ではなさそうです。
かなり具体的な要件が提示されたことで、前評判のような誰にでもチャンスがあるような補助金ではないことが分かったと思います。
おそらく来週中には公募が開始されます。
そこで発表される公募要領を見ないと最終的には何とも言えませんが、今からでも自社の事業計画と照らし合わせ、合致するかどうか検討を始めましょう。