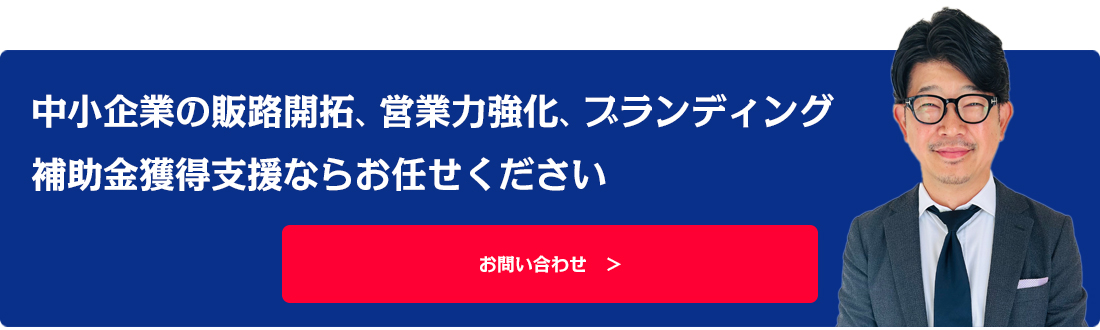最近「デザイン思考」って、よく耳にしませんか?
私はいままで、「優秀なデザイナーが持つ特有の思考方法のこと」って勝手に思ってました。
週末、ある勉強会に参加してこの「デザイン思考」を少し学んだのですが、私が思っていた「デザイン思考」とは、かなり違ってました。
2000年代中頃デザインコンサルティング会社のIDEO社が提唱したビジネスプロセスが「デザイン思考」だそうです。
この会社は、アップルのマウスデザインやiPodの開発、さらには医療機器やキッチン用品、金融商品まで「デザイン」しているそうです。すごい会社ですね。
「デザイン思考」とは、誰でも新しいアイディアを見つけて商品化、サービス化できる画期的なビジネスプロセスです。
とはいってもわかりにくい表現ですよね。
いままでのマーケティング手法では、市場データを客観的に分析をして法則を見出すのですが、「デザイン思考」では、人の行動や言動から、顧客が「気づいていない本質」に迫ります。
これだけ物が溢れている時代に前例や実績を参考しても斬新なアイディアが浮かびませんし、ライバル会社とよく似た商品しか生まれません。こんな時代だからこそ、たくさんの企業が「デザイン思考」に注目しているのでしょう。
では「デザイン思考」の進め方を説明しましょう。
プロセスは大きく3つに分かれます。
それは、①着想②発案③実現です。
まずは①着想です。このフェーズで顧客を「観察」しながら、「潜在ニーズ」を探ります。但し通常の顧客インタビューやアンケートを取るのではなく、顧客の行動や言動を「観察」し、顧客の本質的欲求を見るのです。つまり顧客も気づいていないニーズを探し出すということになります。
次に②発想です。ここでは「潜在ニーズ」から実際の商品サービスのアイディアを作り上げていくフェーズです。
個人で取り組むのではなく、多様なメンバーで取り組み、楽しさを重視するのがポイントです。メンバー内に上下関係を無くし、メンバーの自己防衛心を排除します。誰もが必ず持っている「創造性」引き出すことが重要なのです。このフェーズはチームファシリテーションがとても重要になります。
さらに重要なのが試作品作りです。プロトタイピングと呼ばれますが、できるだけ安価でたくさんの試作品を作るのがポイントです。そもそも試作品というのは、作るだけで時間も費用もかかるために一度作ってしまうとなかなか修正できなかったり、後戻りできない場合があります。それを防ぐためにできるだけ安価な試作品をたくさん作って失敗を繰り返すのです。
最後に③実現です。
ここで大きなハードルが生まれます。それは経営陣を納得させることです。「潜在ニーズ」で作り上げた商品はいままで前例や実績がないので、経営陣が承認しずらいからです。経営陣が「理解」「共感」してもらうために、紙芝居や動画を利用するケースなんかもあるそうです。
上記が「デザイン思考」のステップです。
では企業でこの「デザイン思考」を導入する場合の留意点は何でしょうか?
・メンバーを正当化する(一見遊んでいるようにも見えるので)
・自発的なメンバーを集める(やらされ感では創造性は発揮できない)
・プロセスの後戻りを容認する(日本企業は一番これを嫌うそうです)
・いきなり儲かる事業を期待しない(経営者によくありがちですね)
ということで、トップがこの「デザイン思考」をしっかり理解することがとても重要になりそうです。
古い体質の会社は導入が難しそうですね。
逆に言えば、中小企業であれば社長自らGOサインを出せば、この「デザイン思考」の導入は増えるかもしれません。
実際、ある町工場では既に「デザイン思考」導入して新たな商品開発に取り組んでいる事例があるそうです。
なお「デザイン思考」は以下のような場合は導入しても効果がでないそうです。
・顧客のニーズが明確な場合(顧客のニーズがわからないときにデザイン思考の効果が発揮されます)
・強力なリーダーシップがある場合(あくまでも凡人のための手法です)
要するにスティーブ・ジョブズがいるなら「デザイン思考」はいらないってわけですね。
スーパーマンではなく普通の人が、個人ではなくチームで、前例や実績のないアイディアを事業化させることができる手法がまざに「デザイン思考」なのでしょう。