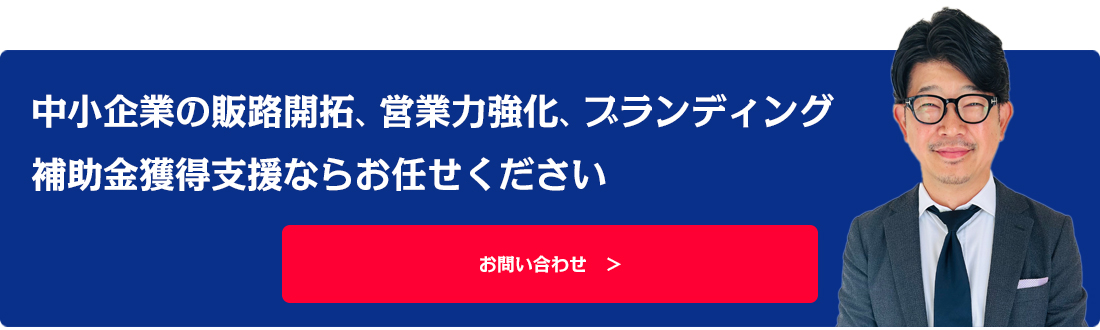昨年中小企業診断士向けに「小規模事業者向けマーケティング講座」というテーマで話した内容を少し文章として掲載しておきます。
私は東京商工会議所のコーディネーターをやっていることもあり、普段から小規模事業者の「マーケティング」分野を支援することが多いです。
もともと法人向け営業職を長年経験していたので、営業コンサルが専門ですが、小規模事業者だと業種はバラバラだし、営業パーソンがいないケースがほとんどです。小売店だと集客は主にWEBになりますので、対法人営業経験だけでは、支援ができません。
営業手段は多数あるので、その組み合わせを含めアドバイスを行ないますが、そもそもその事業者が持つ商品やサービスは差別化されているのか?ニーズにマッチしているのか?自社の強みを活かしているのか?そういった根本部分についてアドバイスを行なうことも少なくありません。
そういう経験も踏まえ、「小規模事業者向けマーケティング講座」を実施しました。
ではそもそも「マーケティング」とは何でしょうか?
マーケティングとは、シンプルに言えば「自然に売れる仕組み」をつくることです。
こちらから売り込まずとも、顧客が商品・サービスを利用してくれる状態です。
ではマーケティングの目的は、何でしょうか?それは自社の商品・サービスを通じて、顧客を喜ばせること、幸せになってもらうことです。
さらにマーケティング施策を積み重ねることで顧客と良好な関係を構築し、再購入、紹介、口コミに繋がり、営業活動の負担が減る効果が期待できるのです。
ではマーケティングを考えるうえで、マーケティングの構成要素は何でしょうか?
それは「誰に」「何を」「どのように」売るかです。
非常のシンプルな表現ですが、いかにここ明確にするかが難しいのです。
「誰に」とはもちろんターゲットとなる顧客です。
「何を」とは提供する商品サービスになります。
そして「どのように」はどうやって商品サービスを顧客に届けるかです。
この3つの構成要素を明確にするためのポイントをお話しました。ここで一部ご紹介しますね。
・顧客と商品・サービスを絞り込むこと。絞り込みにより、自社商品サービスの特長が伝わりやすくなり顧客の興味をかきたてる。あくまでも絞り込むだけで、対象外というわけではないことは注意。
・顧客に優先順位をつけるべし。2割の贔屓(ひいき)客が8割の売上をつくる。
・付加価値を売ろう。いまの時代はQCD(品質・コスト・納期)では勝負できない。
・モノを売るよりコト消費は需要である。現代はモノがあふれているため、価格競争に陥りやすく、商品・サービスは類似化しやすい。よって顧客側の買う目的が見出しづらいため、商品・サービスそのものを買うのではなく体験やストーリーを含めて購入する購買活動を促進する。
機能ではなく価値を売ろう。顧客は意外に自分で商品を選べないものである。顧客に選ばせる場合は選択肢を絞り込むことが重要。選択肢は3つにするのがベスト。顧客には必ずおすすめを伝えること。
講座では、上記のような内容を事例を踏まえ紹介しました。
最後に専門家の立場として、小規模事業者向けマーケティング支援として以下のことを話しました。
①会社や社長が実現可能な支援策を提示する
そもそも経営資源がないのが小規模事業者です。大企業と違い、お金も人材もシステムもありません。よってお金をかけずにすぐに取組める施策を提示しています。
②理論よりも具体策を提示し、明日からのアクションに繋げる
理論では会社は動きません。重要なのは具体的なアクションプランです。アクションから集客や売上に繋がれば事業者も前向きに他の施策にも取り組めます。
③現場社員の意見を聞いて、効果のある改善策を考える
社長だけではなく、現場社員の意見を聞きながら、改善策を考えます。現場のことは社員が一番よくわかっています。現場を無視した施策は効果が期待できません。
④支援日までの間で細かな進捗管理を行なう
小規模事業者の場合、アドバイスを行っても継続的に実施できていないケースが多くあります。よって次の支援日の間に進捗管理を行ない、施策が実施されているかのチェックが重要になります。
⑤PLに直結した目標設定と検証を意識する
マーケティングコンサルタントとの違いは、PLと連動した支援を行なうことです。単に受注数やWEBのアクセス数だけではなく、月次の損益をどう改善するかが重要です。よってPLとマーケティング施策を連動させることが重要です。
このような活動を通じて1社でも多くの小規模事業者の売上向上に役に立てればと思います。