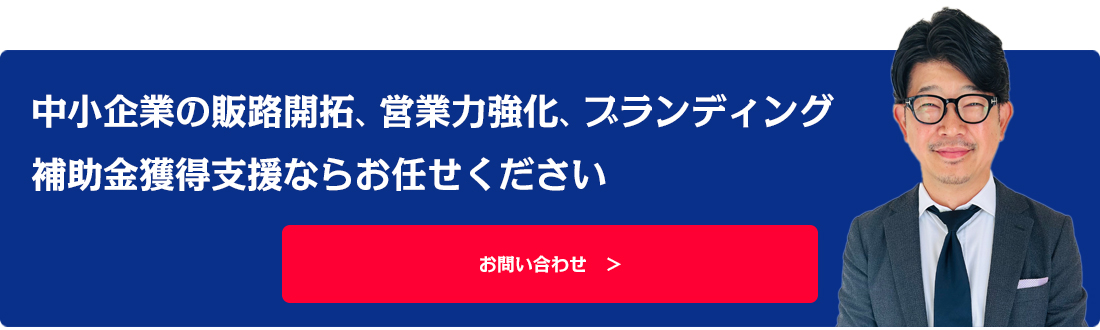近年、中小企業を支援する補助金が多数公募されています。政府にとっては景気の良し悪しが中小企業の業績に判断されるところが大きいですから、今後もたくさんの補助金が中小企業向けに公募されるでしょう。
1.「補助金とは何か?」
そもそも「補助金」とは、何でしょうか?
補助金とは、主に国や地方公共団体等から支出されるお金のことです。
企業にとっての資金調達は通常、金融機関からの融資が一般的です。しかしながら、補助金活用の場合は返金不要で資金調達が可能になります。つまり申請書の内容次第で、国から無償でお金が投入されるわけです。
新たな技術、商品、サービスを生み出すためには、多額の経営資源を投資する必要があります。
大企業と違って、中小企業の経営資源は限りがあります。この貴重な経営資源(ヒト、モノ、カネ、情報)のうち、カネの部分を国が無償で投資をしてくれるわけですから利用しない手はありません。
2.「補助金の効果」とは?
では「補助金の効果」とは何でしょうか?主な効果を3つあげておきます。
1つ目は「業績を上げる効果」です。最新の設備導入は、企業の技術力を高め、競合会社に対して競争優位性をもたらします。それにより発注が増え、業績が上がります。逆に言えば、業績のあがらない補助金活用は意味がありません。つまり補助金をもらうことが目的ではなく、補助金を使って事業を1日も早く収益化することが重要です。
2つ目は、「事業の成長スピードを早める効果」があります。
大きな設備投資や技術開発は、中小企業にとっては大きな負担です。しかしながら投資はタイミングよく継続的に行わないと企業の成長スピードは鈍化します。補助金はその設備投資や技術開発費用を国が後押ししてくれるわけですから、自前の資金を使うよりも当然成長スピードを高めることができるのです。
3つ目は「他の補助金も採択されやすくなる効果」です。
補助金に採択される会社は、他の補助金も採択されていることが珍しくありません。採択されるということは、その会社の事業アイディアに対して国や都道府県が一定の評価を与えた証拠です。他の補助金の採択が受けやすい強い会社ほど、実は補助金を活用し、競争優位性を得ているのです。
3.「補助金活用のデメリット」とは?
ここまで書くと、いいことばかりの補助金活用ですが、当然デメリットもあります。
主なものを説明しておきましょう。
①事務作業が煩雑
申請書作成も大変な手間がかかりますが、採択された後も、交付申請、中間監査、実績報告と多数の事務作業が発生します。事務作業が煩雑で対応できず辞退する企業もあるほどです。
②申請書を書くには長い時間と労力が必要
優秀な申請書は簡単には作成できません。公募要領に書かれた採択基準に則ってわかりやすく記載していくには相当な時間がかかります。専門家に頼む企業が多いこともうなづけます。
③補助金獲得が目的になり、必要ない経費を使うことがある
補助金獲得が目的になり、本体事業には必要ない経費を計上してしまうことがよくあります。そういった設備は結局、業績向上に繋がらないケースが多く、無駄な投資に終わってしまいます。
④ルールを守らないと経費が認められない場合がある
補助金は国民の税金を投入しています。つまり厳格なルールのもとに運用されます。経費ルールを守らない場合は、最悪補助金が下りない場合があります。
4.補助金の現場で感じること
ここから、私が補助金申請を通じて「現場で感じること」を書きます。
①明確な戦略をもつ企業が少ない
補助金活用は本来競争力を高め、業績を向上させるために活用すべきです。そのためには経営戦略、事業戦略、そして商品戦略、サービス戦略が立案されている必要があります。単に「機械を入れ替えたい」とか「補助金を使いたい」という動機が多く、事業を、商品を、サービスをどうしていきたいのか?明確な戦略をもった企業が少ないと感じています。
②資料の作成に慣れていない会社が多い
補助金は書類審査のみで採択が決まることが多いです。つまり資料作成能力で合否が決まるといっても過言ではありません。しかしながら、中小企業で書類作成に慣れているケースはあまりありません。せっかくいい事業アイディアをもっていても、社長が熱い思いをもっていても、その会社に他社にない技術があっても、資料として表現できなければ、補助金を獲得できないのです。
③採択後の事務処理に苦労する会社が多い
補助金には採択後にも、数回の事業報告があります。国の税金を使って事業を行なうのですから、報告義務は当たり前です。しかしながら、事務処理に手間取り、国や地方自治体が求める事業報告ができないケースが意外に多いのです。
ただしこういった会社にも、すばらしい技術や社長のアイディアがあるのも事実です。
だからこそ我々のような中小企業診断士が必要に応じて、申請書の作成代行及び採択後の事務フォローを支援すべきだと考えています。
私が担当した事例を1件紹介します。
埼玉県にある金属加工業の事例です。年商は2億円、従業員は30名。金融機関からの勧めでものづくり補助金を知り、申請を決意しました。しかし、いままで補助金申請は経験がなく、さらに社内に申請書を作成できる人材もおりません。ニーズは単なる「老朽化設備の入替」です。
しかしながら、この会社には多数の職人が在籍し、すばらしい加工技術をもっていました。また大口顧客からの技術的信頼も厚く、この機械が入ることで発注が増えることは間違いありませんでした。
社長は自社で申請が困難と判断し、私に支援を求めました。私は、テーマを「加工部品の精密化に対応できる生産体制の確立」とし、生産工程をフローチャート化しました。さらに技術的課題を数値化し、解決策を明確にしました。さらに開発後のターゲット顧客、販売方法、収益予測を明確にしました。結果、この申請は採択され、無事約2000万円のNC制御付旋盤機を購入し、1000万円の補助金を獲得できました。この設備投資によって大口顧客からの発注が増え、業績が向上したのです。
このケースで言えることは、もし、この会社が専門家の支援を受けず単独で申請していたら、採択されなかった可能性があるということです。自社に高い技術があり、大口顧客からの発注増加も予測できたのにもかかわらずです。このような会社はまだまだ多数存在します。
補助金は来年度、再来年度も次々と公募されます。当然その年によって規模や条件は違いますが、中小企業が日本の経済を支えている事実がある限りこの制度は半永続的に続きます。
この補助金をうまく活用し、技術力を向上させ、競争力をつけることは中小企業にとって必要不可欠です。
だからこそ自力で申請できない中小企業を救うことが、我々中小企業診断士の課せられた使命だと考えています。