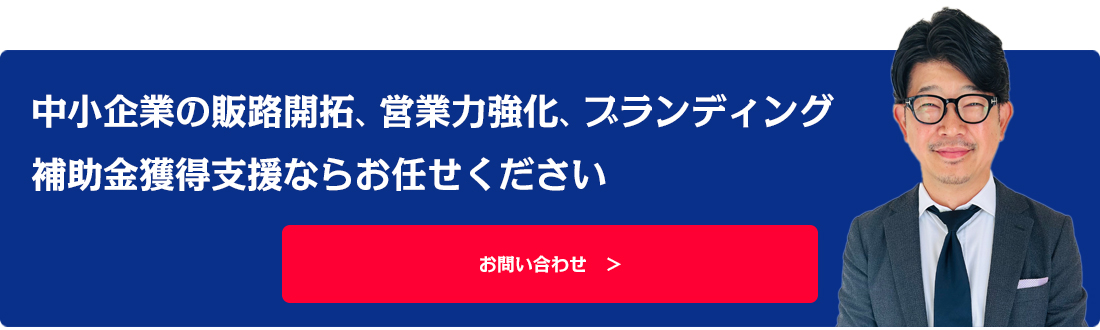ビジネスマンであれば、一度は「問題解決思考」という言葉を聞いたことがあると思います。企業研修の中でも人気のあるテーマのひとつです。本屋に行けば関連する書籍は多数販売されています。しかし本を1冊読んだからといって、なかなかビジネスの現場でうまく使えないのが、このテーマの難しいところですね。
「問題解決思考」とは、日々のビジネス現場で必要とされる普遍的な仕事の進め方のことです。
問題解決の「正解」はありませんが、「手順」は決まっています。
ではなぜこの「問題解決思考」を学ぶ必要があるのでしょうか?それは以下の3つの理由があります。
1つ目は、ビジネス現場では日々問題解決の連続であるから。
2つ目はいままでの経験や勘、度胸だけでは通用しないから。
3つ目は目まぐるしく変化する外部環境に対応するため、意思決定にスピードが必要だから。
特に3つ目は重要ですね。これだけ外部環境が激しく変化する時代に、スピード感をもって対応するためには必須の思考技術なのです。
そしてこの「問題解決思考」を身につけると、以下のような効果が生まれます。
・単なる思い込みではなく、事実に基づいて問題を発見・分析できる。
・問題・原因・対策を、根拠のある明確なものにすることができる。
・問題解決のステップを、再現性を持って実行することができる。
特に「再現性」というのは、ビジネスの世界で非常に重要です。つまり「問題解決思考」を身につければ、最も効率的に、目指すゴールにたどり着くことができるのです。
但し、ゴールにたどり着くために必要なのは思考技術だけではありません。
問題解決には原因追及する思考力に加え、解決策を具現化する「実行力」も備わっていなければなりません。
では肝心の「問題解決思考」の手順は以下の通りです。
①問題がどこにあるのか?を特定する。
②その問題の原因は何か?を追求する。
③問題を解決するにはどうすればよいか?解決策を立案する。
こう書いてみると非常にシンプルなのです。
ではステップ毎に解説していきましょう。
まず①ですが、「問題」とは「現状」と「あるべき姿」のギャップであり、そのギャップは解決すべき事象です。
「あるべき姿」というのは、その個人や組織がもつ目指す目標です。目標のない人には問題意識は生まれないといいますね。
つまり「あるべき姿」がなければ、現状とのギャップがわからないので、問題は特定できません。
「現状」と「あるべき姿」を比較しやすくするためには、単位を揃え、数値で表すとわかりやすいといわれています。
例えば
■現状:収益が100万円の赤字
■あるべき姿:収益が100万円の黒字
■問題:収益が200万円足りない
というように問題を特定するのです。
足りないのが200万なのか?2000万なのか?2億なのか?それによって問題解決の度合いも変わってきます。なぜ単位を合わせ数値で示すかといれば、そうすることで関係者の認識を一致させることができるからです。
では、以下の文章で問題が特定できますか?考えてみてください。
・私はイチローのようにボールを打てない。
・私は昨年よりも体重が0.5キロ増えた。
・私は休暇が取れずにストレスが溜まっている。
「あるべき姿」も「現状」も、そのギャップもわからないので問題を特定できません。問題は、当事者の価値観次第になってしまいます。それではビジネスの世界では通用しません。だから正確に問題を特定するために単位を揃え数字で示すのです。
次に②です。「なぜなぜ」を繰り返し、真因(根本原因)を特定します。いわゆる「なぜなぜ分析」ですね。
問題をツリー状に分解して整理する「ロジックツリー」を使うことが多いです。
では、なぜ真因を特定する必要があるのでしょうか?
例えば、Aさんの体調が悪いとします。そこでAさんの症状を心配したBさんが、飲み物をあげたり、食べ物をあげたり、横になるよう勧めたり、悩みを聞いてあげたりしますが、Aさんは一向に体調が治りません。Aさんに症状を詳しく聞くと、お腹が痛く、昨日夕食に食べた魚にあたったのではないか?というのです。そして、Bさんが胃薬を渡すとAさんの症状は治りました。
つまり真因に対して対策を打たないと、全く問題解決にならないからです。
ビジネスの世界では、対策を打って効果がでないことはよくあります。その場合、真因を特定できていない可能性を検討しましょう。
この「なぜなぜ分析」ですが気をつけなければならないポイントがあります。それは以下の通りです。
・これ以上「なぜなぜ」ができないところまで繰り返しているか?
・問題と真因に因果関係があるか?
・真因を解消すれば、問題解決できるか?
・真因の解消は当事者が対応できるか?
特に真因が「他責」になると、まったくもって問題解決とはいえませんので注意が必要です。例えば天候や、競合他社の値下げ、増税、法改正等、自分では解決できないことが真因になっていないか?ということです。
そしていよいよ③になります。解決策の立案です。ポイントは以下の通りです。
・実行可能な策になっているか?
・解決策は複数あるか?
・施策を実⾏する人は誰か?
・いつまでにやるのかが明確に決まっているか?
・対策はコインの裏返しになっていないか?
コインの裏返しとは、例えば問題が「当社への発注が100万円減少している」に対して、対策が「当社への発注を100万円増加させる」になっている状態です。何の問題解決にもなっていない状態ですね。
こうなるのは、②のステップの検討が明らかに足りないケースが多いです。
以上が「問題解決思考」の手順です。
「問題解決思考」は、知識ではなく技術です。技術つまりスキルです。スキルの上達は、実践しかありません。実際のビジネス現場で使い続けることで技術レベルが上達します。
1日1回でいいので、実際遭遇したビジネス現場の事象を当てはめて考えてみてください。
繰り返し実践で使い続けることで、「問題解決思考」が自分の中に定着します。