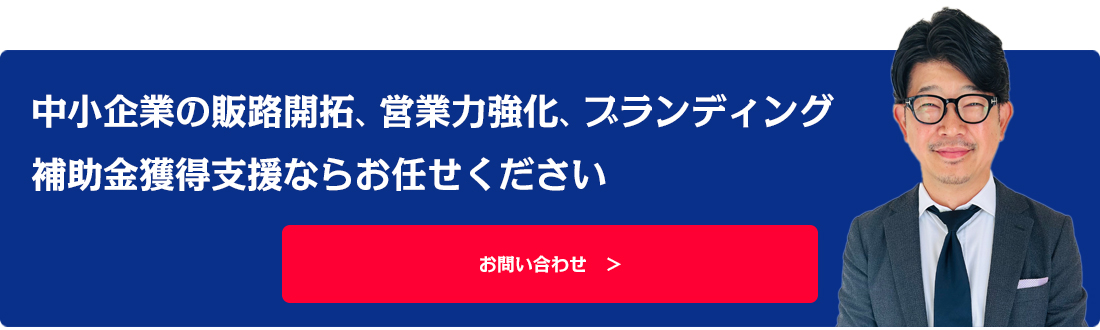私は、あるコンサルティング会社の定期勉強会に参加しており、そこで人材開発や組織開発を学ぶ機会をもらっています。
人材開発と組織開発の違いも明確でなかった私にとっては毎回非常に刺激的な内容です。
この勉強会は単なる知識の習得ではなく、受講者同士で議論を重ね、いわゆるグループワークやクラスワークで結論を共有するようなスタイルです。

最近の企業研修もこのような傾向が強くなっており、ネットで調べればすぐわかるような知識や情報は、研修する意味が薄く、価値が低下している証拠なのでしょうね。
私は普段中小企業の事業戦略を中心にコンサルティングすることが多いですが、最近は組織開発についても一緒に課題に取り組むことが少なくありません。
そのような課題解決には、この勉強会で取得した知識が役立ちます。
ちなみに人材開発と組織開発の違いですが、まず人材開発はその人個人の能力開発にフォーカスした内容になります。それに対して組織開発は、組織に属する上司部下や社員同士、部署間などの「関係性」にフォーカスした内容になります。
一般論ですが、例えば人は自由を求めますが、組織に自由を求めるとまとまりを欠いたり、個人プレーに走ったり、協力しなかったり様々な弊害がでます。だからこそ様々な規律やルールをつくるわけですが、それが厳しすぎると人は何も考えなくなり、ルールありきで行動するようになります。そのような組織は創造性や革新性の欠けた組織になってしまい、時代の変化に取り残されてしまうわけです。だからこそ自律性を持ちながら組織を機能させるには、社員の能力開発が必要になるのです。さらには組織を管理し活性化させるリーダーは、部下の能力を見極め、適正な役割分担を行ない、さらには部下のやる気を引き出す必要があるのです。
この勉強会で、今後のビジネスパーソンにおいて必要な能力は何か?について学びがありましたのでご紹介します。 2つの能力が必要とのことでした。
ひとつは「自己認識力」です。私の理解では、「自己認識力」とは自分の能力を客観的に把握することであると考えています。言うは簡単ですがなかなか難しいことですね。
もし自己を過剰認識する状態になれば、いわゆる人の意見を聞かなくなり、自己の成長を止めてしまいます。また自分のことを棚上げにして相手への批判に終始してしまいがちです。また環境のせいにしてしまい自らの行動を振り返らなくなります。
逆に自己を過少認識する状態になれば、自分に自信がないために課題への踏み込みが浅くなったり、失敗を恐れたり、すぐ諦めたり、自分の能力を必要な場面で発揮できなくなったりします。
つまり自己を正しく認識しないと、ビジネスパーソンとしての成長が見込めないのです。
私はアセスメントの仕事も定期的にやっているので、自己認識力のバランスのいいビジネスパーソンは稀であり、どちらかに傾向が偏る場合が多いといえます。ちなみにアセスメントとは第三者による客観的な視点を取り入れて社員の能力開発をうながす評価手法です。なのでこれからは自己認識力を高め、社員個々が能力を高めるためにアセスメントの需要も高くなると考えられます。

もう一つは「受容力」です。最近はSNS等ネット上で自由に自分の意見を発信できるようになりました。その影響なのか?全く知らない他人に厳しい論法が増えた気がします。自分の価値観を優先し、他人を認めない傾向が強くなったように感じます。リアルなビジネス社会では、ダイバーシティとか、リスペクトとか、共存共栄とか他者を認めるべき概念や言葉が出てきますが、一般世論としては、そういう考えは後退しているように感じるのは私だけではないはずです。
組織開発の観点でいうと、組織が「受容力」を失うと組織弾力性を失い、組織崩壊が一気に進むといいます。組織の弾力性とは、変化の激しい外部環境に柔軟に対応できる組織のことです。つまり「受容力」が低下すれば、様々な価値観をもつ社員を周囲が認めず、多様な人材が育たなくなり、これから起こりうる様々な環境変化に対応できず組織が衰退するということです。
「自己認識力」と「受容力」を高めることが、今後のビジネスパーソンにとって必要な能力といえますね。