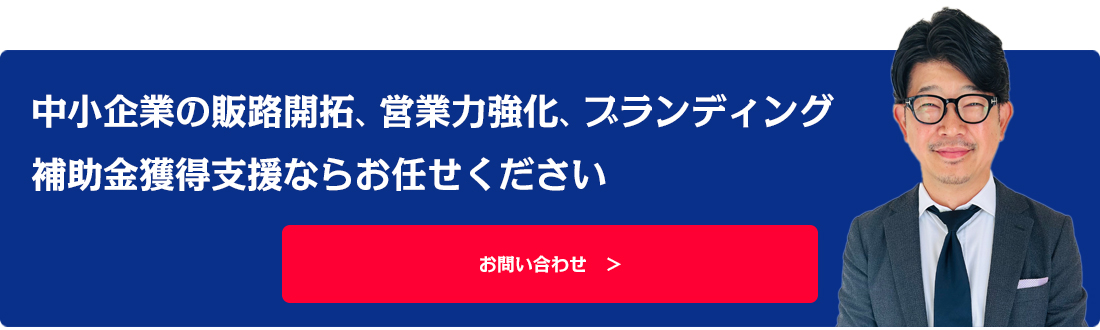皆さんこんにちは!中小企業営業支援の津山淳二です。中小企業向けに営業強化、ブランディング、補助金支援を行なっております。
本日は、久しぶりにブランディングネタです。そのなかで、製造業ブランディングについて解説します。特に、素材や部品などを企業向けに販売しているような会社でどのようにブランディングを行なうべきかをお話ししたいと思います。
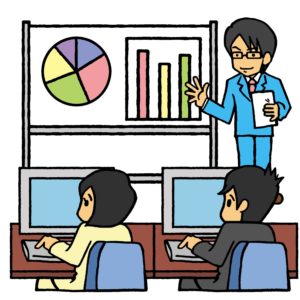
まずブランディングには大きく3つの種類があります。
それは、BtoCブランディング、BtoBtoCブランディング、そしてBtoBブランディングになります。
ブランディングで最もイメージしやすいのは、BtoCブランディング、BtoBtoCブランディングではないでしょうか?例えばスターバックスやマクドナルドはまさに一般消費者にダイレクトにブランディングを展開しているわかりやすい例といえます。またコカ・コーラは、スーパーやコンビニに置かれており、我々はそういった流通網に足を運び商品を購入します。これはBtoBtoCブランディングのわかりやすい事例といえるでしょう。
ではBtoBブランディングはどういう事例があるでしょうか?例えば最近CMでよく見かける販促サービスのラクスル、名刺情報システムのサンサンは、活用する人が多岐に渡るため、知名度も高く、またサービスの認知度も進んでいます。こういった提供するサービスのイメージがつきやすい企業は、ブランディング施策も理解しやすいですね。
しかしながら冒頭に説明した、素材や部品などを企業向けに販売しているような会社でどのようにブランディングを進めればいいのでしょうか?今回テーマに挙げている製造業ブランディングはまさにこのような会社はどうブランディングに取り組むかを考えたいと思います。

まず、製造業ブランディングを語る前に、製造業のBtoB取引における特長をここで説明します。
①購買は合理的に決定する
BtoC取引と違い、感情的や勢いに任せた意思決定することはほとんどありません。取引の多くは、数社の提案結果を比較し、合理的な判断のもとに決定します。部品や材料などの決定は、自社商品にフィットするか?安定的な供給が可能か?品質基準を満たすか?など、様々な条件をクリアせねばなりません。
②長期的取引になりやすい。
合理的な検討結果で取引が決まるため、一度決まると、よっぽどのことがない限り、長期的取引になりがちです。取引をやめる場合も、各セクションが納得する理由が必要になるため、同様に時間がかかります。つまり一度取引が始まると比較的安定的な受注が見込まれます。
③組織的な取引である
組織的な取引のため、購買を検討する現場と決済機能をもつ購買部門等、意思決定の部署が多岐に渡る場合があります。そのため営業は一つの窓口だけでなく網羅的に情報を収集する必要があります。
上記のような製造業のBtoB取引における特長を説明すると、以下のような指摘をよく受けます。
「ブランディングよりも、優秀な営業を育成することが大事ではないか?」
ということです。

製造業にとって、優秀な営業を育成することは重要な経営課題です。だからといって製造業にとってブランディングが必要ないわけではありません。
では製造業にとってなぜブランディングが必要なのでしょうか?
まずは、なんといっても新規開拓が必要だからです。当たり前ですが、会社は新規顧客を定期的に取り続けないと衰退してしまいます。そのためにブランディングを強化することで、新規開拓を優位に進める必要があります。他社に比べブランドが浸透していれば、例えば展示会でも、ブースに足を運んでくれる可能性が高くなり、集客力が増し、営業がやりやすくなるのです。
2つ目は、製品やサービスでの差別化が困難なためです。この情報化社会のなかで、自社の製品やサービスだけでライバルに競争優位性を保つのは難しいです。そこでブランディング強化して、顧客に印象付けをする必要があります。例えば「監視カメラならA社」というブランドイメージが定着すると、たとえライバルB社と品質面で大きな差がなくても、A社が選ばれる可能性が高まるのです。
最後に優秀な人材採用のためです。最終製品を販売していない場合、なかなか一般消費者に自社の存在を知らせることが難しくなります。その場合、採用活動で苦戦するケースが多くなります。最近製造業のCMが多いのは、明らかに採用を強化する狙いがあります。ブランディングを強化することで、自社の魅力を発信し、採用活動を有利に進めることで、安定した事業継続を行なう必要があるのです。

ここで改めてブランディングとは何か?を説明しておきます。
ブランド・マネージャー認定協会によれば、“「こう思われたい」というブランドアイデンティティ(BI)を確立し、顧客が思うブランドイメージを一致させる”と定義されています。
つまり企業側は、自分が思われたいイメージを、絞り込んだ顧客にメッセージを届け続けることが大事なのです。
では改めて製造業ブランディングとは、何でしょうか?
以下の3つに分けられます。
①企業ブランディング
その企業そのものをブランディングします。具体的には、SDGsへの取組や環境への取組、地域貢献等が該当します。従業員教育の取組みや、社員自身の活躍なども企業ブランディングに影響を与えます。特に製造業の場合、取引が長期にわたりますので、その会社がどのような社会貢献を行なっているか?地域社会にどう貢献しているか等、事業の継続性を高く評価します。
②製品サービスブランディング
製品やサービス自体をブランディングします。製造業の場合、その製品を使うことでどのような課題解決が可能か?どういった効果がでるかが、製品サービスブランディングに影響を与えます。具体的な数値効果や導入事例などがブランディングに効果的です。
③技術ブランディング
その会社が持つ技術をブランディングします。具体的には産学連携の取組や特許取得などが該当します。

では、製造業のブランディングはどう進めればいいのでしょうか?以下のステップで説明します。
①何をブランディングするのか?決める
まずブランディングする対象は何かを決めます。先ほどご紹介した①企業そのもの②製品サービス③技術の中から何を選択してブランディングするか決めましょう。それにより、顧客は誰か?顧客に何をイメージしてもらうか?ライバルとの差別化ポイントはどこか?も変わってきます。
②ブランドアイデンティティは何か?を決める
ブランドアイデンティティとは、顧客に「こう思われたい」というイメージの総称です。具体的には、顧客は誰か?提供したい価値は何か?ライバルとの差別化ポイントは何か?を明確にすることです。ここがブランディング活動すべての基盤になります。
③販売戦略をどうするか?決める
ブランドアイデンティティを踏まえ、販売戦略を構築します。具体的には、製品のパッケージやネーミングをどうするか?顧客へのアプローチ方法をどうするか?アプローチの際に使うメディアをどうするか?など検討することは多岐に渡ります。
ここで注意すべきポイントは2つあります。
①ブランドアイデンティティが決まっていないのに、先に販売戦略を立てないこと。
ほとんどの会社は先に「どう売るか?」を考えがちです。大事なことは、どういうイメージを顧客に持ってもらうかです。特に製造業の場合、相手は、現場の技術者等、専門的知識をもつ人が多いと思いますが、そういった人達にどう販売するかを考えるのではなく、どういうブランドイメージを持ってもらうべきかを自社内で固めることが重要です。
②顧客にブランドアイデンティティをイメージさせるには、一定の時間が必要であることを理解すること
ブランドイメージを持ってもらうことは、簡単な事ではありません。短期的には難しく、一定の時間が必要です。自社製品を購入する可能性のある技術者との接点において、いかに継続的に、一貫性のあるメッセージを発信し続けることがブランディング成功のカギになります。
以上が製造業ブランディングの進め方になります。今後、自社の売上向上のためにブランディングを検討している方のご参考になれば幸いです。